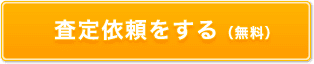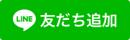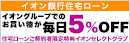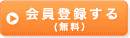Q1.金融機関から督促の通知がきたら?
A1.住宅ローンを借り入れている金融機関など、債権者から支払督促状や郵便物などが届いたら目を通すことが必要です。返済方法の見直しに関する内容や、法的な手続きをとるといった警告文です。
Q2.連帯保証人と連帯債務者とは?
A2.連帯保証人とは、債務者がローンの返済ができなくなった場合に、債務者に代わり返済義務を受ける方のことです。 連帯債務者とは、ローンを借りた債務者と一緒に借入金を返済している方のことです。
Q3.住宅ローンを滞納したら、一括返済の請求があったんですが?
A3.一般的に、滞納し始めて1~2ヶ月は、金融機関より郵便で「競売など法的な手続きをとります」といった文面の督促状が送られます。 3ヶ月を過ぎると、「期限の利益の喪失」の手続きをとり、一括返済の請求をします。そこで返済ができない場合、任意売却か競売の選択となります。
Q4.任意売却とは何ですか?
A4.金融機関などから強制されるのではなく、任意売却取扱い業者などの専門家や弁護士などが間に入って、債務者が不動産を売却することです。
Q5.任意売却をした後の残債務はどうなりますか?
A5.残債務も引き続き返済します。金融機関などの債権者との交渉によっては返済期間や月々の返済額を変更できる場合があります。
Q6.任意売却で売れない場合ってどんな時ですか?
A6.不動産売買の契約が成立しなければ、延期を申し出るか、金融機関が競売を取り下げることがなければ競売へ移行します。
Q7.任意売却したら今の家に住み続けることはできますか?
A7.2通りの方法があります。
①買戻し
親子、兄弟など親族・親戚に今の家を買い受けてもらう。直接売買できる場合だけでなく、一旦身内ではない第三者に購入してもらい、その後親族が購入するという方法があります。
②リースバック
投資家などの購入者へ不動産を売却しますが、一定の賃料を支払う事で、継続してその不動産を利用する方法を言います。交渉によりリースバック終了後にその不動さを買い戻しができる場合があります。
任意売却のメリット
○誰にも知られずに売却が可能
任意売却の販売方法は一般の中古不動産売買と変わりません。そのため、債務に苦しんでいることを周囲に知られることはありません。一方、競売になれば、情報は裁判所で閲覧することが可能となり、新聞や業界紙、インターネットなどで掲載されるため、競売にかかったことが周囲に知られてしまう場合があります。
○残債務の返済の負担を軽減
任意売却で不動産の売却をしても、住宅ローンを完済できず残った差額のことを残債務といい、不動産を売却した後も返済をしなければならない義務があります。しかし、任意売却の場合には、この残債務の返済期間や月々の返済金額の調整について債権者と交渉ができます。 売却するときに必要な仲介手数料、不動産管理費、滞納している税金専門業者への報酬や相談料などは債権者から任意売却による売却代金を配分して精算されるため、原則として債務者の持ち出し負担はありません。
○不動産受け渡しなどの柔軟な対応
債権者との交渉によっては、引越し費用や当面の生活資金などで便宜を図ってもらえる場合があります。また不動産の購入者との交渉次第では、転居先が決まり引越しが完了した後に物件の引渡しができる場合があります。 競売では落札者の意向次第で、立退きを要求され、引越し費用も自己負担となる場合があります。
○競売よりも高値で売却
任意売却の場合は、以下の点で購入者にとって競売と比較して有利なため、高値がつきやすくなっています。
・購入の事前に不動産の内部や情報を確認できる。 ・保証金の預託が不要。 ・一括購入でなく、住宅ローンが組める。
○住み続けられる可能性がある
任意売却の場合なら親族・親戚などに買い受けてもらい、不動産を残すことができます。 また投資家などの購入者へ不動産を売却し、賃貸物件として不動産を利用するリースバックという方法もあります。交渉によっては、リースバック終了後にその不動産の買い戻しができる場合があります。
任意売却での流れ
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)から借り入れをしている場合の任意売却の流れを1例として挙げます。
①住宅ローンの延滞、滞納
②住宅金融支援機構の窓口銀行から督促
住宅ローンの返済を滞納した場合は、まずは融資を受けている金融機関へ連絡をして、返済方法の相談が必要です。
③任意売却の相談
3ヶ月以上ローンの返済ができないと信用情報機関に登録されます。その後、不動産の売却の意思が決まったら、不動産業者や弁護士・司法書士などへ任意売却の相談をし、返済状況、債務内容などの確認を行います。
④任意売却業者の選定
売却価格や条件等を検討して、任意売却業務を行なう業者を選定します。
⑤専任媒介契約の締結
物件の販売活動を始めるにあたり、任意売却の専門業者と専任媒介契約を結びます。この契約によって業者は債権者・抵当権者との交渉ができます。
⑥住宅金融支援機構へ書類を提出
任意売却業者が販売活動をする旨を、住宅金融支援機構に書類を提出し伝えます。
⑦住宅金融支援機構から売り出し価格の提示
⑧抵当権者への任意売却の報告
業者が債権者へ任意売却の依頼を受けた旨を連絡します。
⑨物件の販売活動の開始
債権者・抵当権者から任意売却の許可が出ると、業者は不動産の販売を開始します。不動産業者間のデータベースへの登録及び情報公開や不動産の売却のために、業者のホームページや不動産情報ポータルサイト、折込チラシ、広告などに情報が公開されます。
⑩購入申込および債権者・抵当権者との交渉
債務者と債権者・抵当権者との間で売買価格の条件が折り合えば、契約となります。そして、売買価格を元に抵当権者への返済配当計画書を作成して、債権者・抵当権者と交渉します。この時点で、任意売却後の残債務の返済条件の相談も行います。
⑪売買契約の締結
債権者・抵当権者から返済配当に了承が出たら、売買契約を締結します。
⑫残金の決済、所有権移転、物件の引き渡し
決済場所は、購入者が融資を受ける金融機関の最寄りの支店になります。売却代金を購入者から受け取り、所有権移転に必要な書類を専門業者に預けます。
競売
競売とは、住宅ローンなどの融資を借り入れている債務者がローンの支払いが困難になった場合、金融機関などの債権者が、ローンの回収のために、債務者の所有する土地や建物などの不動産や担保物件の売却を裁判所に申し立て、強制的に売却することです。
不動産物件は裁判所から委託を受けた不動産鑑定士が調査をした上で、裁判所により最低売却価格が定められ、最高値を提示した入札者が所有権を落札します。買い手は低い価格で落札しようとするため、一般的に売却価格は市場相場価格の5~8割程度の水準となります。そのため、通常の不動産売買よりも売却価格は下回るケースがほとんどです。 その他に、相続の場合に財産物件を分ける際にも競売を利用し、その売却代金から相続人が代金の分割を行ないます。
○競売のデメリット
①市場の相場価格より5~8割程度安く落札されるため、処分された後の残債務は任意売却のときよりも多くなります。
②残債務の支払い義務は任意売却のときも同じですが、債権者との交渉の間もなく落札されるため、残債務の返済について柔軟
な対応をしてもらうことは期待できず、支払いをめぐるトラブルも少なくありません。
③落札後に立ち退くまで時間的な余裕もなく、強制的に迫られることがあります。
④連帯保証人がいる場合、処分後の残債務の請求が連帯保証人に対して行われ、その支払いができない場合、連帯保証人の不動産も競売にかけられることがあります。
⑤競売にかけられたことが裁判所から公告されるため、周囲の方に知られる場合があります。
⑥競売にかけられた時点で、関係業者の訪問を受けたり、落札を希望する投資家などが自宅周辺を見にきたりするなど、精神的なストレスも多くなります。
任意売却での必要書類
必要書類は、金融機関など債権者によって対応が異なります。また書類の届け出や受け取りについても郵送や、窓口へ出向く場合などがありますので、予め確認しておくことが必要です。 住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の例を挙げます。
○原本が必要な書類
・本人の印鑑証明書
○コピーで大丈夫な書類
・物件の売買契約書および重要事項説明書 ・間取り図 ・登記済権利証(登記識別情報が発行されている場合を除く) ・住宅ローンの督促状など ・土地および建物の評価証明書 ・固定資産税および都市計画税の納付書 ・マンションの場合は管理会社名およびその連絡先
○記入、署名押印が必要な書類
・専任媒介契約書もしくは専属専任媒介契約書 ・委任状 ・任意売却に関する申出書 ・抵当権抹消応諾申請書 ・実査チェックシート ・生活状況申出書 ・マンション現状報告書